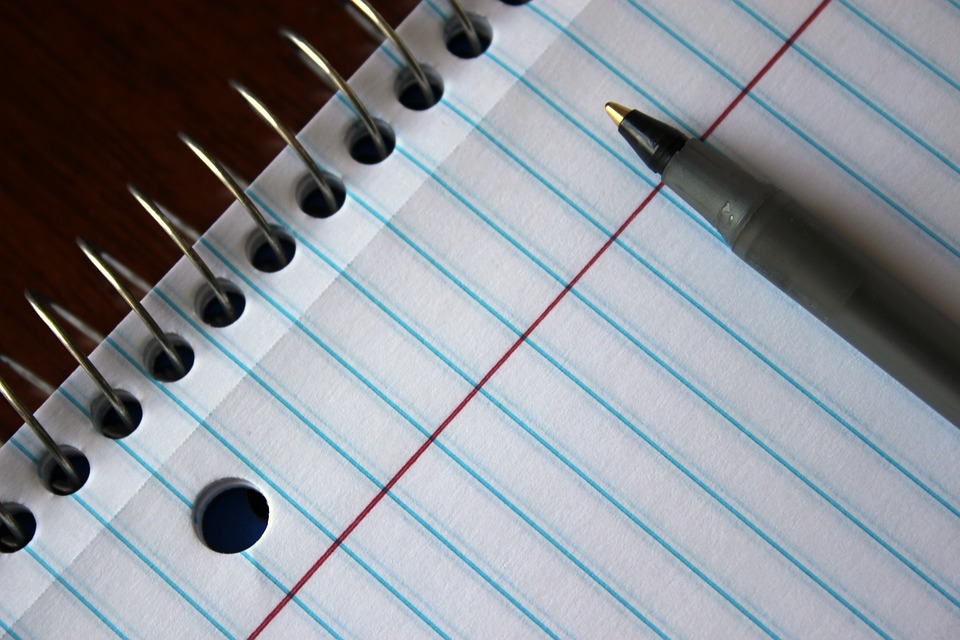
生徒との日々 (1) アルベルト
こんにちは、Erinaです。
今日は私の仕事のことを書きます。(タイトルは暫定です)
今年8月からスタートした新学年、私は同じ学校の Independent Study Program に配属されました。
このプログラムは、例えば出席日数が足りなくて卒業が危ういとか、家庭の事情で毎日学校に通えないとか、様々な事情がある子供達のための場所で、通常の学校のようなストラクチャー(1時間目とか)がありません。
子供達は個別化されたレッスンを消化し、卒業に必要な単位を取ります。
私が現時点で受け持っているのは約30人。
年齢は8年生(日本の中2)から12年生(日本の高3)までで、授業内容も
Math 8
Integrated Math 1 (IM1)
Integrated Math 2 (IM2)
Statistics
の4クラス分とバラバラです。
そんな特殊な環境なので、やはり特殊な子達がやってきます。
家族の生活費のためにバイトを掛け持ちしている子
Depression/Anxietyを持つ子
両親を亡くした子
いじめで登校拒否になった子
心臓手術をする子
ドラッグリハビリに通う子
トラブルで退学寸前の子
・・・などなど、映画やドラマのような世界がぎゅっと詰まっている教室です。
そんな中で目立つのがアルベルト(仮名)15歳。
10年生のメキシコ人の彼は、読解力が2年生レベルと診断され、母語はスペイン語、ADHDと行動障害を持ち、家族の誰も高校を卒業していません。例にもれず、彼もまた昼間は親の引越会社を手伝っているので、週の半分は仕事というハンディキャップのフルコースです。
彼の学力が年齢相当ではないことは私もすぐに気づきました。
彼がもつ様々な学習障害から、学校ではケースマネジャーがつき、カウンセリングを通してもっと様々なことがわかってきました。
読み書きは苦手だけれども数字は強い方で、因数分解なんかもシステムがわかればスラスラできてしまう、なんてことも。
しかしその中で気になったのが、「僕はここで何も学んでいない。学校に来る意味が見出せない」という彼の言葉でした。
数学に限らず、もう何年も「教育」というものから置き去りにされてきたアルベルトは、自分が何のために学校に来るのか、学校の価値は何なのか、に疑問を持ち続けていました。
家族はどうしても彼に高校卒業をしてほしいと思っていたし、私もどうやって彼に高校数学を身に付けさせようかと試行錯誤する日々。
プロジェクトベースの勉強をしたり、仕事と結びつけたり、別科目のカリキュラムも勉強したり、先輩教師達にも相談して出た答えが、
「学びたいことを彼自身に決めさせよう」
でした。
こんな目から鱗な答えがあったなんて、と自分でも驚いたけれど、この結論はそれ以上に驚くほど明らかでした。
次の日、アルベルトをオフィスに呼んで、ケースマネジャーとミーティング。
私:「ねぇ、ここで何かを学んでいる気がしないって言ってたよね。」
アルベルト:「うん。」
私:「じゃあさ、どんなことをやったら、あなたは学んでいる気持ちになると思う?どんなことが今の自分自身にとって必要だと思う?」
ア:「数学で?」
私:「うん、そう。」
そう言うと、彼はしばらく黙って考え込みました。
そして一言、でもはっきりと言ったのです。
“Times table.”
私の中で何かがストーンと落ちて、それは本当に音になって聞こえるくらいでした。
私:「かけ算?それが必要だと感じるのね。」
ア:「うん。」
彼はわかっていたのです。
自分にとって何が必要か。
そしてそれを勉強したいと思えた。
私:「よし、じゃあそれやろう。」
ア:「かけ算?良いの?」
私:「良いよ。だってあなたはそれを必要だと感じるんでしょ?」
ア:「うん、感じる。」
私:「オーケー、じゃあどうやって進められるか考えておくね。でも IM2(通常の高校数学)の方も同時に進行するからね。」
ア:「わかった。」
そう言うと、彼はすっきりした顔でオフィスを出て行きました。
“Times table.”
ポツリとそう言ったアルベルトの横顔が私の中に焼き付いていました。
Times table とはアメリカで2〜3年生が学ぶかけ算表のことで、12×12までが表になっています。multiplication table, multiplication chart なんて呼ばれることもありますが、同じものです。

そうか。
彼の中で、数学はそこで止まっていたのか。
読解レベルも2〜3年生ということだから、やっぱりその辺りからだんだんと学校での内容に距離を感じ始めたんだろう。そう考えると、もう7〜8年間も、彼は教室で置き去りにされてきたことになる。
その現実が悲しくて悔しくて、怒りよりも悲しみがこみ上げてくるのをぐっとこらえて、じゃあ何をどうしようか、と考えました。
とりあえず、うちの子達が使っていた xtramath のかけ算をやらせよう。
でもまず初回は Times table を実際に書き込ませて、どれくらい知ってるかチェックだな。
次の日、アルベルトに真っ白な Times table を渡して言いました。
私:「わかるところからで良いからやってみて。完璧に埋めようと思わなくて良いから。」
ア:「オーケー。」
そう言うと、彼はわかるところからやり始めました。それを見ていると、面白いことに気づいたのです。
彼は、対角線上、つまり二乗のところから埋め始めました。
1×1=1
2×2=4
3×3=9
4×4=16
・・・と、12×12=144 までちゃんと覚えている。
面白いなぁ。常識にとらわれてないな。
私:「そこからやるんだね(笑)。」
ア:「えっ。変?」
私:「いや、良いよ。全然オーケー。続けて。」
そう言って、私は黙って見守ることにしました。
アルベルトはその後、一の段、二の段、五の段、十の段なんかをやり、他の段をちょろっとやって半分くらい埋めました。
ア:「思ったより知ってた。」
私:「あ、そう?良いじゃない。まずはここからスタートね。明日はこの練習用のプログラムを用意しておくから。」
ア:「オーケー。」
そう言って彼は英語のクラスに行きました。
そういえば、今日は文句一つ言わなかったな。
私の中で色々なことが、ひとつひとつ、確信になっていきました。
同時に、これらの生徒達との何気ないやりとりから、この社会にある闇や希望が見えてくることにも気づき始めました。
それはまた別の記事に書くとして、とりあえず、かけ算から始めて、6月までに10年生の数学を仕上げること。
クリアな目標が見えた今、霧の中を手探りで歩いている感覚はなく、むしろ何をどうすれば良いかわかったので、あとはそれをやるだけなのです。