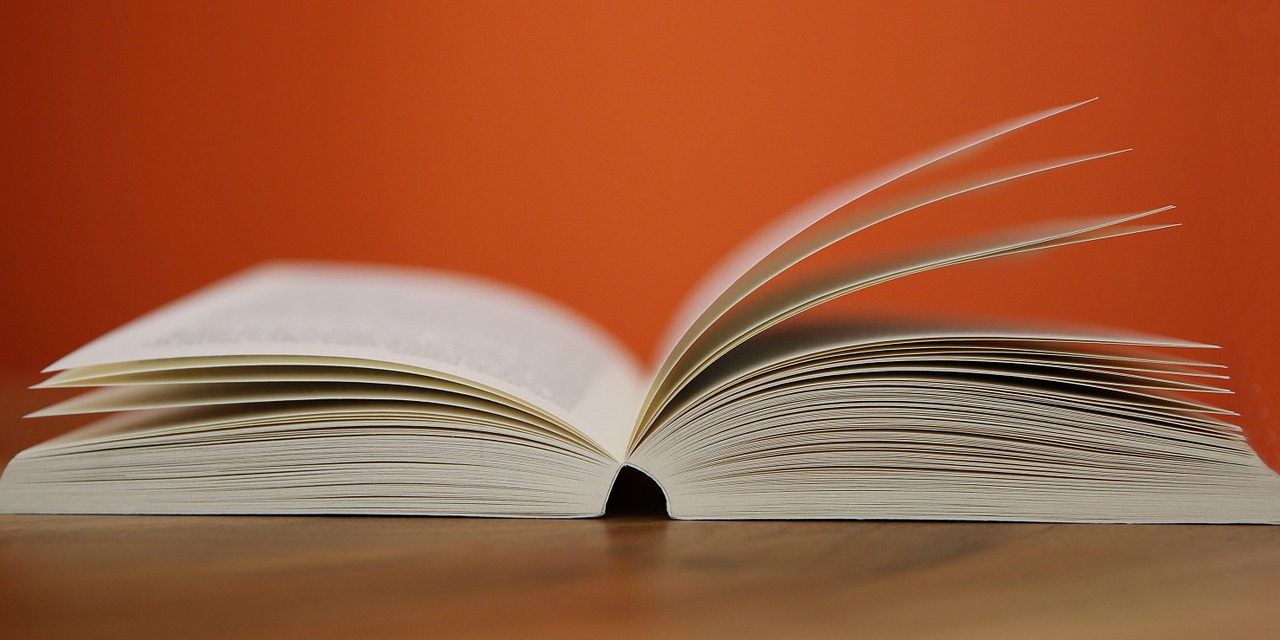
大人になっても勉強する意味
こんにちは、Erinaです。
みなさんは「勉強」が好きですか?
「好きなわけないジャン」
「大人になってやっと勉強から解放されたのに」
なんて思う方もいるかもしれません。
私は自慢じゃありませんが、勉強は大嫌いな子供でした。(爆笑)
宿題なんていつもギリギリまで手をつけず、始業式前日にクラスメートに写させてもらったり、高校の数学なんていつも赤点で追試の日々だったり。超ダメダメでした。
そのくせに好きな教科の成績は学年でトップクラスだったりと、とても「ムラ」のある子供だったと思います。
そんな私がアメリカに来て、2児の母になってまで「学校に戻りたい!」(I want to go back to school!) と思うのは、アメリカで「勉強することの楽しさ」に目覚めたからでした。
勉強って、何のためにするんでしょう?
考えたこと、あります?
「数学の微積分とか、歴史の年号なんて知ってても、社会で役に立たない!」なんてよく言われますけど(私はこの主張は間違ってると思いますけど)、実際はどうなんでしょう。
アメリカ人は大人になっても勉強する人が多いです。
仕事に直結しているものもあれば、趣味でやりたかったことを勉強する人もいます。
それはひとえに「そういう環境が用意されているから」で、私のようにいくつになっても好奇心旺盛・チャレンジ大好き人間には夢のような国なのです。
読者のみなさんの中にも、私のようにこっちにフラフラ~あっちにフラフラ~とまでは行かなくても(笑)、「アメリカで何かを身につけたい」「きちんと何かを勉強したい」と思う方はたくさんいるはず。
特に私たちのような英語を母国語としない外国人にとって最適な場所が、コミュニティカレッジ(コミカレ)や、Continuing Education(生涯教育)という場所だったりします。
コミカレは4年制大学へのステップストーンとしてだけでなく、まさに「大人のための学校」の役割も果たしています。
(アメ10でMikaさんがこんな記事を書いてくれているので参考にどうぞ)
アメリカのコミカレやContinuing Education(継続教育)という概念は日本には存在しないものなので、なかなかうまく説明されていなかったり、理解されていないことが多くて残念なのですが、私が一留学生、それも日本ですら社会経験のない若者として経験したコミカレ時代は、やはりアメリカで生活する上で、ものすごく意味のある時間でした。
それはただ単に必須科目の単位を得ることだけでなく、何よりも「アメリカ人たちの中でもやっていけるんだ」という自信を植え付けてくれたし、アメリカの弱肉強食という競争社会でも走っていこう!というモチベーションになりました。
つまりは「神経が図太くなった」のです。笑
それは、一番最初の授業で課題を聞き取れず、提出日に大焦りでやることとか、それを教授に説明するために、つたない英語でもなんとか伝えようとするとか、差別的な教授に授業登録させてもらえないとか(この教授は後日、解雇)、まぁとにかく授業がチンプンカンプンとか、そういうアメリカ生活で必須の「場数」を踏めるチャンスがそこにはギッシリと用意されていました。
今では笑い話ですが、当時はもちろん大焦り、汗ダラダラなエピソードです。
外国人留学生に理解のある教授もいれば、ない教授もいる。
親切なクラスメートもいれば、そうでないクラスメートもいる。
勤勉な学生もいれば、そうでない学生もいる。
変な学生もいれば、親友になれる学生もいる。
そういう「ごっちゃり感」はまさにアメリカという国の縮図で、そんな中で「どうやってサバイバルするか?」という日々の練習は、5年後、10年後に、アメリカの企業で仕事にアプライし、面接をし、雇われ、多様な同僚たちと仕事をし、ボスに意見し・・・という「リアルワールド」でのトレーニングになるのです。
私がコミカレに行っていなければ、今ほど「アメリカ企業で働く」ということにも固執していなかったかもしれませんし、アメリカ社会の懐の深さを感謝することはなかったと思います。
渡米から13年。
アメリカで「一人でもやっていける」と思えるようになるまで、これだけの時間がかかりました。
アメリカ人旦那が健在であるとか、結婚生活が円満であるとかに関わらず、予測できない「何か」があっても「たぶん大丈夫だろうな」、つまり家族4人がなんとかしながら生きていけるだろうな、と今は思えます。それは経済的なことだけでなく、精神的、社会的なものも含まれているのです。
留学生としてアメリカにやってきたときは、まさか自分がこのような形で「自立」というものを手に入れるとは思わなかったですし、ここに行き着くまでに、どんなことを乗り越えていかなければならないのか、さっぱり無知でした。
今になって思うことは、アメリカで一人でやっていく、というのは簡単ではないということ。
「自由の国アメリカ」でその自由を手に入れるには、それなりの代償があり、努力なしで誰にでも与えられるものではありません。
そのプロセス中には、頭がおかしくなるんじゃないか?というくらいの逆境もやってきます。
世界中、誰も味方はいないんじゃないか?というくらいの孤独感も経験します。
それでも戦い続けるのは、得られるものがそれだけの価値があるからとみんな知っているからです。
13年前の私には、お金も、経験も、コネも、英語力も、情報も、家族も、居場所も何もありませんでした。
あったものはただひとつ。
「日本に帰らない覚悟」
それだけは絶対に揺るがなかった。
私は「今の自分がすごい」なんておごる気は全くないですし、常に自分はまだまだだな、と思い続けています。
けれど、「これまでの自分の経験が、もしかしたら誰かの背中を押すきっかけになるのかも」と思えるだけの出会いがありました。
だから、伝えます。
何事も、時間と努力が必要です。
でもかけた分だけ、必ず戻ってきます。
アメリカはそういう国です。
Do not give up, and be patient.
Keep your eyes open and grab it when it comes.
そういう姿勢で能動的に働きかければ、必ず何かしらのドアが開く、ということを学んだのは、アメリカの学校だったのです。
では、明日からは実際に、アメリカの大人の学校を紹介してみたいと思います。
Erinaさん、こんにちは。いつも楽しみにしています。更新されるとすごく嬉しいです。
ちょっとプライベートな話で、答えたくなかったらスルーしてくださいね。
でも聞きたいことがあるんです。笑
アメリカに13年前にErinaさんが飛んだとき、お金も家族もコネもなにもなかったっておっしゃっていました。
でも日本にはご家族がいましたか?
日本のご家族と離れること、どう感じていましたか?
わたしには日本に家族がいます。しかもひとりっこ。家族の老後は?死後は?とかまだ来てもいない未来にも不安がたくさんあります。
私は渡米することを決めていますが、決めたからには後悔しないことに決めました(決めてばかり?笑)
でも、決めたとはいえ、不安なのです。
とくに家族のことは。
病気になったら?入院したら?介護が必要になったら?とか。
Erinaさんはどう考えていましたか?
もし差し支えなければ教えてください。
Nanaさん、こんにちは!
コメント、ありがとうございます。
日本の家族と離れることについて、ですね。
実は私も一人っ子で、母ひとり、子ひとりの母子家庭でした。
なので、母は「よく娘を行かせたね~」と周りから言われたそうです。
私は母に反抗心があったわけではなかったですが、やはり若いながらに自分の力を試してみたかったし、結果として母と距離を置いたことが良かったと思います。
日本を離れたことで、色々なことが冷静に見えるようになったし、昔は話せなかったことも話せるようになりました。
・・・と、それって精神的なものですよね。
母の老後とか介護については、私も母も、「自分の人生は自分のもの」という考えがあるので(たぶん)、あまり私に介護などを期待していないと思います。
この件については、19歳で渡米したときは全く考えてはいなかったことで、最近になって現実的になってきたところですが・・・。
親の老後については、アメ10でこんな記事も書いたので、読んでみてください。
http://takeiteasyinamerica.com/?p=16880
「介護」と一口に言っても、本当に様々で、子供として何ができるか?も変わってきます。
それはそのときになってみないとわからないし、わからないことのために、現在の可能性を捨てることはしない、と私も決めました。(決めてばかりです。笑)
自分の人生を捨てて、年老いた親の面倒を見ることだけが、親孝行だとは思わないですし、それはこれまでに築き上げてきた親子関係から見極めるものかな、と今は思っています。
もちろん、違う考えの方もいらっしゃると思いますが。
答えになったかなぁ・・・?
Erinaさん、こんにちは!コメントありがとうございます。
答えになっています。ありがとうございます。親の存在がいつもいつもひっかかっているのです。
でもわたしも親なので息子のことを考えると、好きにしてほしいって思うし、私の将来より自分の将来を大事にしなさいって思うのです。
でも私の親はきっと近くにいてほしいだろうなって思うと、心が痛みます。
というのも今までたくさんの愛情をもらって、たくさんの心配、迷惑をかけてきて、なにもお返し出来てない気がするのです。
その両親が私が近くにいることを望むのに、海外に行こうとする娘。笑
一人っ子なせいか、なんなのか自由気ままでほんとErinaさんのいうように独立心が強い。(一緒にしてすみません。笑)
そしてアメリカに魅せられてしまったのです。
アメ10読みました。大切なのは柔軟性。響きました。
わたしもまずは自分のやりたい、目の前のことからチャレンジして、それから考えようかなと思いました。
答えはどんな形でも出てくるはずですよね!!
Nanaさん、こんにちは!
そうですね。
子供の幸せは親にとって大事ですね。
現実として年老いる親のケアをどうするか、というのはやはり、大人としての会話が必要だと思いますが、それと「幸せ」は別ものだと考えるようにしています。
海外生活する上で、自分の幸せ、親の幸せ、子供の幸せを、客観的に見極める必要があるかもしれませんね。