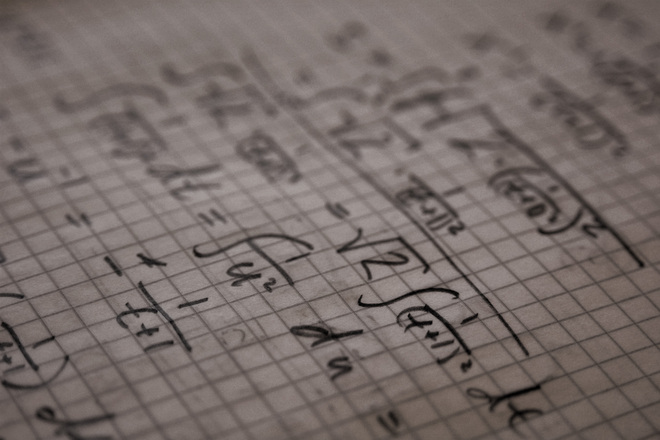
私が苦手な数学を克服した方法(後編)
前回の続きです。
続くCalculus II(微積分II)も、同じ教授のクラスに登録した私たち3人。
内容はぐんと難しくなりましたが、一緒に勉強する時間も増やし、何かと要領も良くなった私たち。
「数学専攻にしてみようかな・・・。」
そんな考えがセメスター中に思いつきます。
当時、生物学専攻だった私でしたが、そこに行き着くまでに取らなければならない化学(Chemistry)の実験(ラボ)が嫌になってきた頃でした。(苦笑)
「ラボは時間もかかるし、準備も大変だし、器具とかチェックするのが面倒くさい・・・。」
と、今考えるとどうしようもないエクスキューズですが、性格的に向いてなかったのでしょう。そういうのが好きな人もいますからね。
Calculus IIは、決して楽ではなかったものの、3人全員Aでセメスターを終了。
他のクラスでも要領を得て、どのクラスでもAを取れるようになってきた頃。
「私、賢くなってきてる!大学生っぽい!」と人生で初めて感じた時期でした。
ここでちょうど大学一年目が終了。
進路を変えるなら、今でしょ!
と思い立ち、「数学メジャーにします!(だって面白いんだもん)」
カウンセラー:「オーケー。」(あっさり)
次はいよいよMath252。Calculus IIIと呼ばれる、Multivariable calculus(日本語だと・・・多変数微積分?)のクラスです。
スケジュールの事情で、同じクラスを取れなくなったキムくん。今回はGuyと2人になりました。
「2人になっちゃったね。」
この頃から、それぞれのメジャーに必要な授業(エンジニアリングメジャーの彼らはPhysics・物理をたくさん取っていた)も忙しくなります。Study Groupの時間はめっきり減り、個別で勉強することが増えました。
加えて、この授業はG教授ではなくて、厳しいと噂の別の教授。
「このクラスは、Lower Division(大学1~2年次)で一番タフな数学の授業だから、心して取り掛かるように。」
と半分脅しとも取れるアナウンス。
「ゲゲ・・・・マジかぁ・・・。」
今までのCalculs IとIIは、大学受験勉強の残りでなんとかなってきた部分もあったのですが、いよいよ私にとってもまっさらな部分がほとんど。
言われた通り、内容はとてもタフでした。
一問に何時間もかけて、それでもできなくて、数日間その問題のことばかり考えてみたり、テスト前に朝6時まで徹夜でGuyとテスト勉強し、フラフラになってテストを受たこともあります。
だけど、面白い。
たとえば、海底の石油や天然ガス採掘。海底表面の凹凸や、資源の大きさなどを、どうやって採掘前に割り出すか。コストに見合うだけの資源をどうやって見つけ、どうやって採掘するか。
表面がなだらかでない山中に、道路や建物を建設するときに、コストから見て最も適切なルートやデザインは何か。
山をくりぬいて建てた円形のビルはガラス張り。必要なガラスはどれくらいか。
Saddle(乗馬に使う鞍)みたいな表面分析も「これも数学でできちゃうの?!」という発見が増えました。
現実社会での応用がどんどん入ってくると、「うわ!超面白いジャン!」と思うようになったのです。
そんな流れで、Applied Mathematics emphasis in Financial MathematicsというメジャーでSan Diego State University (SDSU)の3年次に編入します。
コミカレでは、メジャー:一般教養=50:50くらいの割合でしたが、いよいよ80:20とか90:10とメジャーのクラスのウェイトが増えます。
同時期にバークレーに編入したキムくんも、UCSDに編入したGuyもここにはいません。
「まぁ、勝手はわかってるんだし・・・。」
と、とにかく1人で黙々と勉強する日々。課題の内容も濃い。授業も濃い。アメリカ人学生たちも必死です。
だけれど、数学が嫌になったことはありませんでした。
3~4年次での数学では、応用分野も広がり、それぞれの数学が研究でどんな風に使われているか?がとても身近になってきました。
「やっぱり数学って面白い。数学を勉強した後に、そんな職業があったなんて知らなかった。」
Actuarial Modelingの授業では、Life Insurance(生命保険)の値段の決め方、Annuityの月額の決め方などをProbability(確率)を使って割り出します。
Risk Managementの授業では、株やデリバティブのポートフォリオのリスク計算をして、どんなポートフォリオを与えられた状況下で持つべきか?という計算をします。
Operations Researchの授業では、Supply Chainと呼ばれる倉庫管理の最善策や、郵便配達員の例などが面白かったです。
Partial Differential Equationというクラスでは、Fluid Mechanics(流体工学)が面白くて、「これを使えばフリーウェイの渋滞も解析できる!」ということも発見。
Numerical Analysis(数値解析)はデジタル画像の処理スピードを理解するのに役立ったし、ミリタリーのSonarや電波だって、三角関数で説明できます。
「こういうことを最初から、(噛み砕いて)子供に教えれば良いのに。」
と思うようになりました。
そうすれば、数学はつまらなくて難しいものから、実生活に密着したオモシロイものになる。
私は自分の「数学チンプンカンプン時代」を思い出して、「こういうことを教えてくれる人がいたら、きっと数学への意識も違ってただろうな」と思うようになったのです。
世の中には様々なルールや設定があります。
私たちは消費者として、利用者として、それを当然のように受け入れ、疑問も持ちません。
「どうしてガソリンが昨日まで$3.79だったのに、今日は$4を越えているのか?」
「どうしてフリーウェイはこういうデザインなのか?」
「どうして#2のバスルートはこうなのか?」
「どうしてこのデジカメは$350で、あっちは$280なのか?」
「どうしてProgressiveの保険は、GEICOに比べて安いのか?」
などなど、考えたことがありますか?
こういうの、全部、理論をベースに決めている人がいるんです。
そして、それが数学をやってきた人たちだったりします。
新卒で就職が決まったとき、こう思いました。
「数学が大嫌いだったあの頃の自分が、すごく遠く感じる。でも、不可能じゃなかった。」
そして「誰でも、何でも、やればできる」と自分の身をもって証明したことを実感したのです。


私も数学は大の苦手で、わからなすぎて高校の数学が睡眠の時間となっていたくらいでした。
大学に入ってからも苦手意識は克服できなかったのですが、
ビジネス専攻でとったクラスの先生の教え方がとても上手で、
初めて数学でAが取れて嬉しかったことを覚えています。
しかし苦手意識は克服できず今に至るのですが、
エリナさんの記事を読んで、”え〜そんなことまでわかるの!”と興味が
とっても沸きました。その数学の面白さがわかるところまで理解してみたいです。
Akiさん、こんにちは!
お~!すごい!!
ここにも数学を克服してAを取った方が!!
「やり直してみたら、できた」って嬉しいですよね。
「もう一回やってみよう」ってすごく勇気がいることだし、そのご褒美だと私は思ってます。
これからも、数学の例について書いていこうと思っています!
読んで興味を持ってくれる方がいて、私も嬉しいです。
こんにちは
僕は現在18歳で浪人中なのですがコミカレに進学したいと思ってます。
しかしお金がなくあの手この手で貯めていますがいつ行けるかもめどが立っていません
質問なのですがアメリカではコミカレに入学希望の際こういう空白になってる期間というものはやはり考慮されてしまうのでしょうか?
Kichiさん、こんにちは!
質問いただき、ありがとうございます。
コミカレに進学するまでの空白の時間ということですが、私個人的には関係ないと思います。
アメリカのコミカレには、高校を卒業したばかりの人だけでなく、仕事をしていてキャリアアップのためだったり、何らかの理由で進学できなかった学生がたくさんいます。
・・・と思ったので、専門家(サンディエゴのコミカレで留学生入学課で働く)のMikaさんにも相談してみたところ、同じご意見をいただきました。
MikaさんはGrossmont Collegeで働いています。彼女のメールアドレスもいただいたので、もし直接、質問したいことがあれば連絡してみてください。mika.miller@gcccd.eduです。
頑張ってくださいね! Good luck!
はじめまして
24歳、日本で私立大文学部卒の者です。
大学生活後半になって今まで触れてこなかった数学や物理の面白さに出会い、卒業後、センター試験から国公立大学を目指しましたが不合格でした。
現在はSE職で就職活動をしていますが、大学再入学して数学とコンピュータサイエンスを学びたいと、いろいろと調べているところです。
erinaさんの数学の話を読み、数学の学び方が非常に面白いと感じました。衝撃を受けました。
また、コミカレと聞くと語学学校というイメージでしたが、数学や物理など専門基礎科目を学ぶ場だとは初めて知りました。
現在独学で高校数学でいう数3を今進めているところで、今後働きながらこのまま国公立大のセンター試験・2次試験の受験科目を勉強をしていくか、
もしくは大学2年レベルまでの数学物理学を独学で勉強してから編入試験を目指すかを考えていましたが、お金を貯めてコミカレに進む道もありなのかもしれない、と思うようになりました!
ありがとうございます!
かっぱ3さん、こんにちは!
コメントありがとうございます。
そうですね、コミカレ(コミュニティカレッジ)は、4年制大学の1〜2年時と同じものが学べて、同じ単位に換算されるので、様々なクラスがあります。
理系科目だけでなく、心理学、哲学、文学、歴史、外国語など、また職業訓練的な看護学などもあり、その需要は毎年高まっています。
コミカレについて質問がありましたら、いつでもご連絡くださいね!
頑張ってください!
子供が大きくなるにつれ日本とアメリカの高校、大学の数学の違いを調べてこのサイトに来ました。私は日本では数学は確か常にテストは平均20点くらいで2とかでしたがアメリカの大学に編入したあと取れる教科が当初理数系のみだったため、不得手だった微積分のコースも取りました。テキストは分厚いけどほとんど読まずともAがとれた笑い話をしています。アメリカのCALC IIIでさすがに日本の数学レベルではわかならくなって来て断念しました。それでいまだどのように学んだことを応用に使えるのかわからないです。断片的に公式があってテストがあればこなす、という程度だったためとても教えられる自信がないです。是非是非わかりやすく子供達にも興味を持って教えられるように応用できる例からサイトでご教授してくれるとありがたいです。
コミカレでの一番最初のセメスターでとる授業について悩んでいて、このブログにたどり着きました。
英語、数学、物理、化学合計で18ユニットは初めてのセメスターではきついでしょうか?
そして、コミカレで習う理系科目は一般的な日本の高校の授業と比較して難易度が格段と上がったり、もしくは下がったりはするのですか?
kochiさん、こんにちは。
最初のセメスターなんですね。楽しみと不安が半々なの、私も覚えています。
そこで英語・数学・物理・化学の18ユニットということですが、最初のセメスターとしてはちょっと厳しいんじゃないかなと思います。
もちろん、これは私個人の感じ方なので、kochiさんの能力を知らないでのアドバイスですが、私だったらちょっと減らします。
英語と数学はキープして、物理と化学はどちらか一つにしますね。
というのも、物理と化学って、内容によりますが、ラボが入ってきませんか?実験はかなり時間が取られます。レポートをまとめたり、準備したり、リサーチしたり。なので、ラボがあるものは1セメに1クラスが良いと思いますよ。
やはり最初のセメスターなので、手応えを感じ取るために、そんなに自分を追い込まないほうがのちのちのためです。
後でとればAが取れたかもしれないのに、あせってとって、最終的にCだったら悔しいと思いますよ。
カウンセラーにも相談してみてください。
頑張ってくださいね。
忘れてました。
こんな記事も書いたので、ぜひ参考にしてみてください。
もう読んだかな?
http://innadeshikoway.com/?p=2786